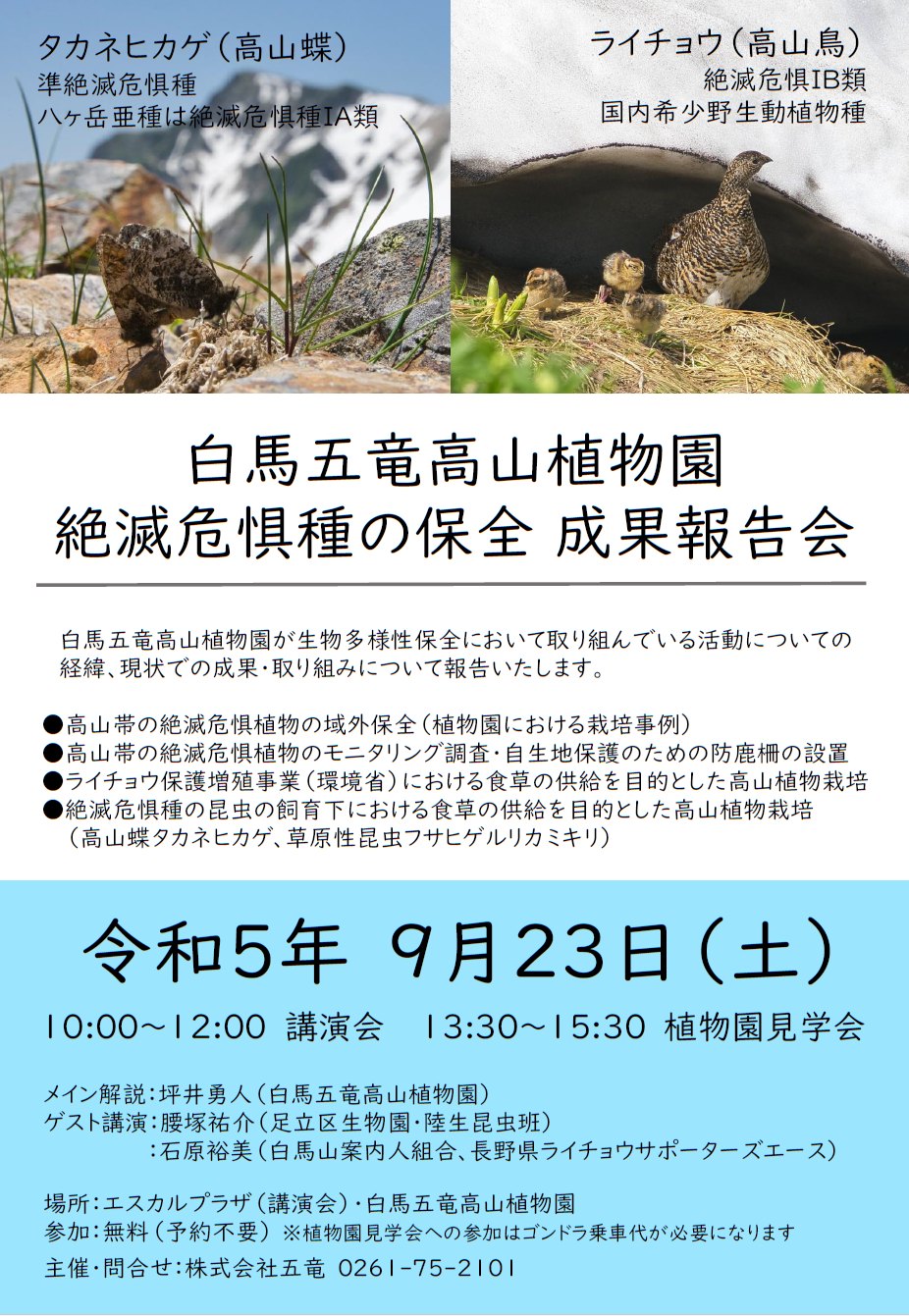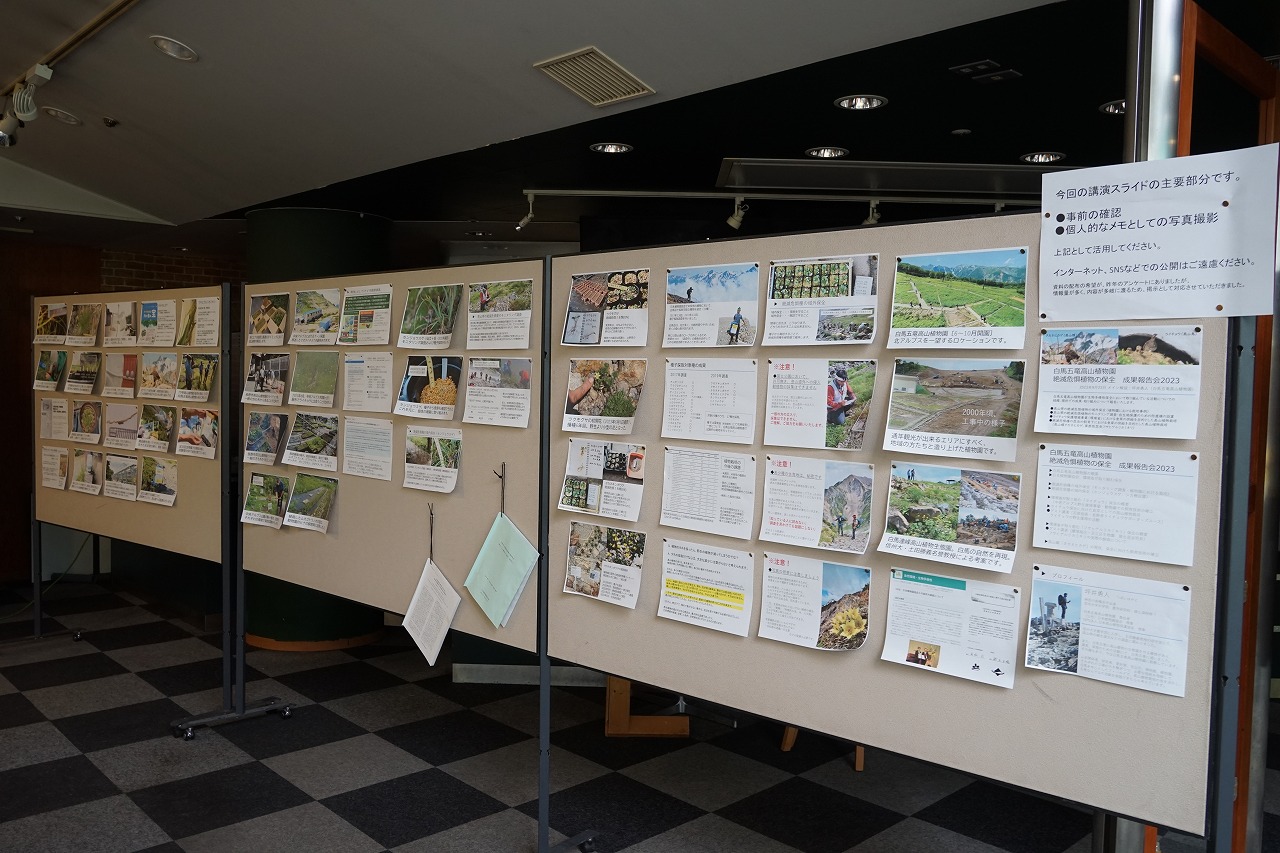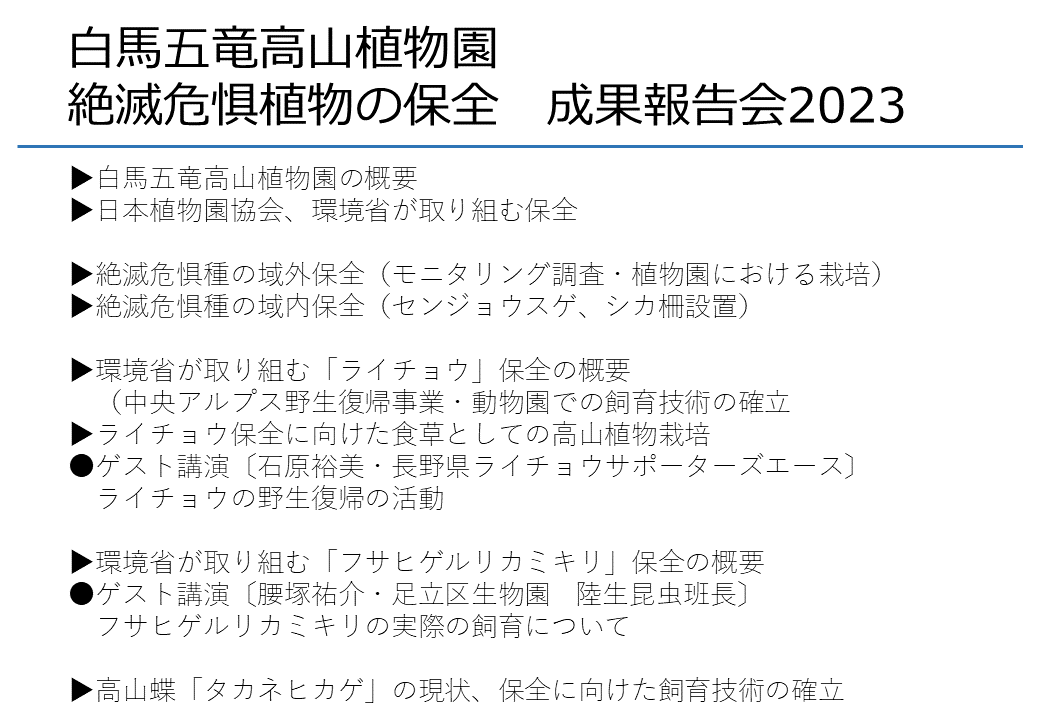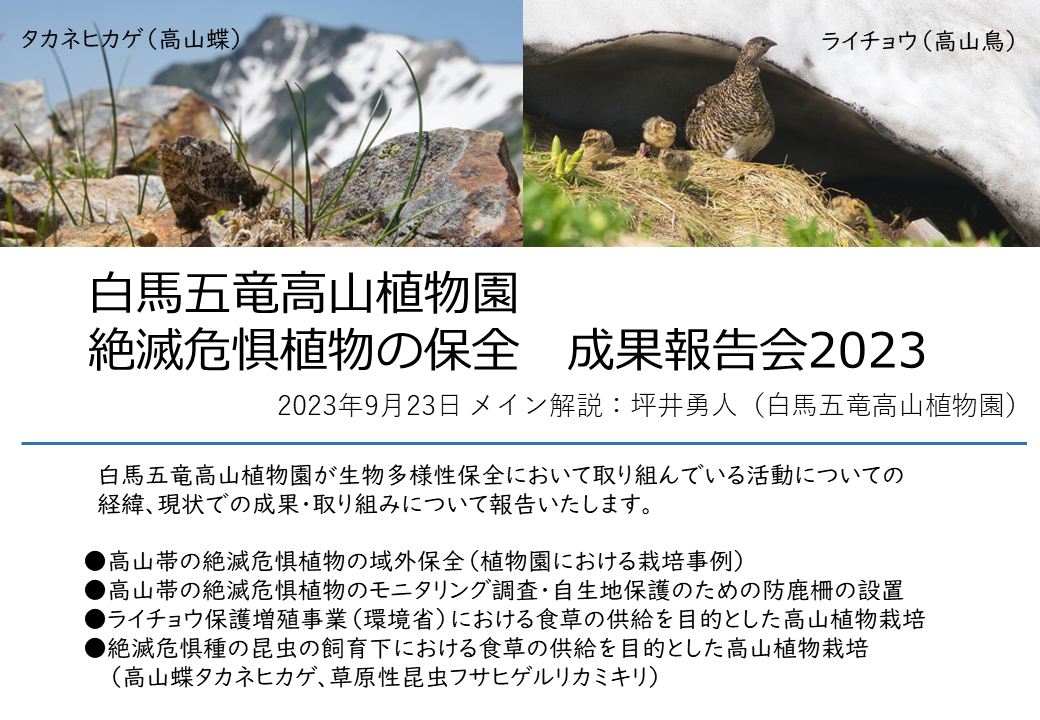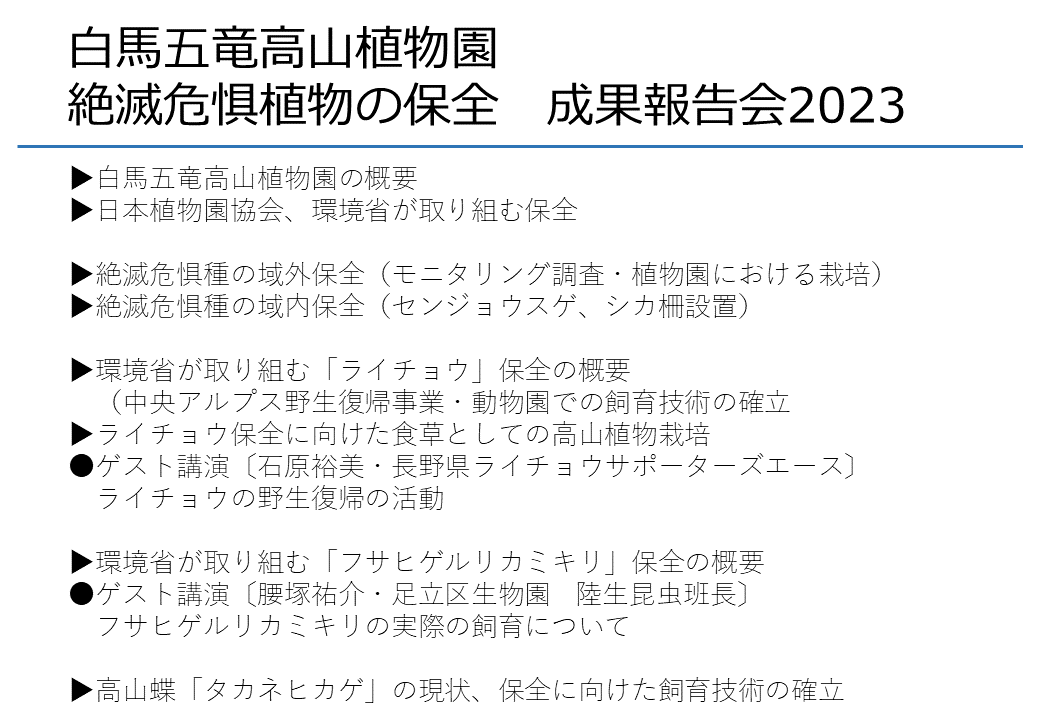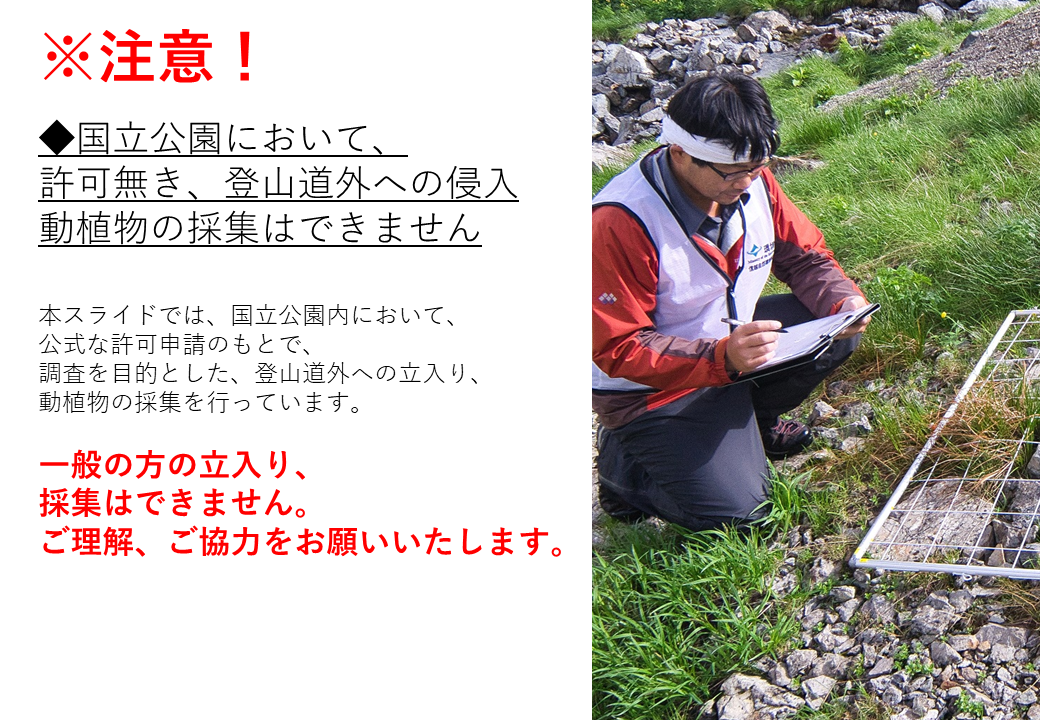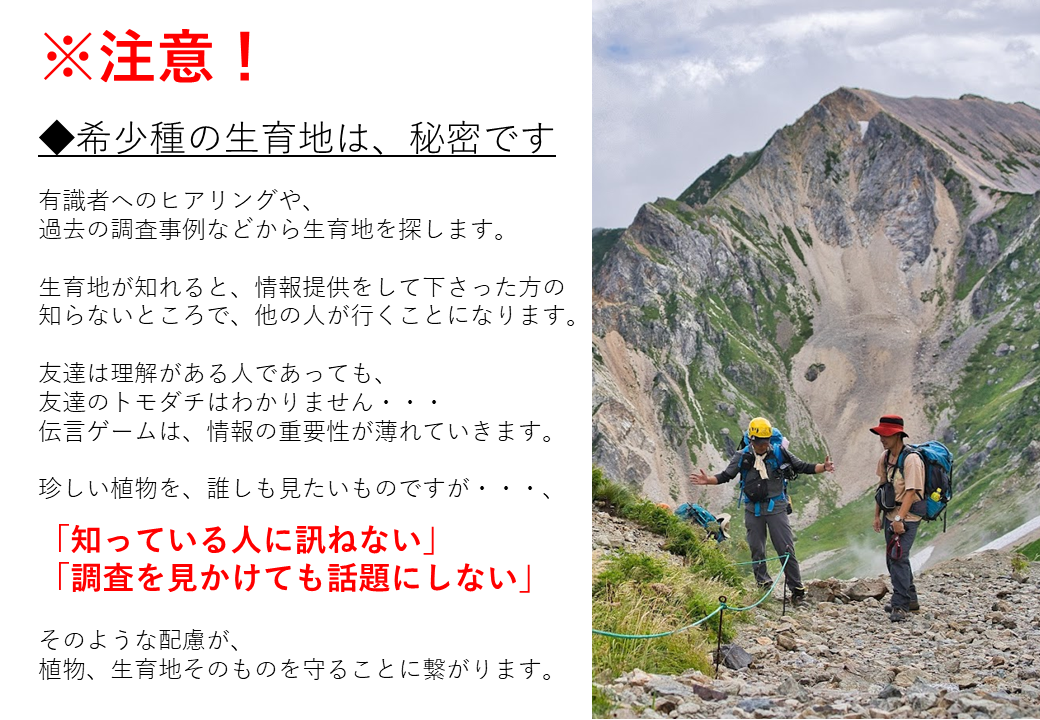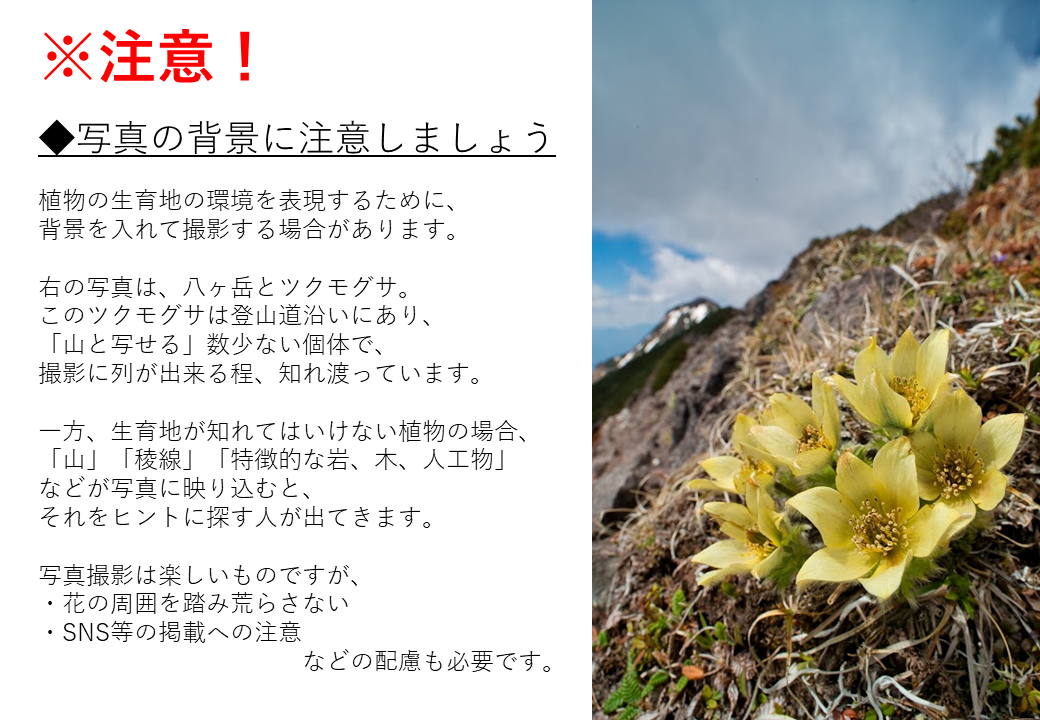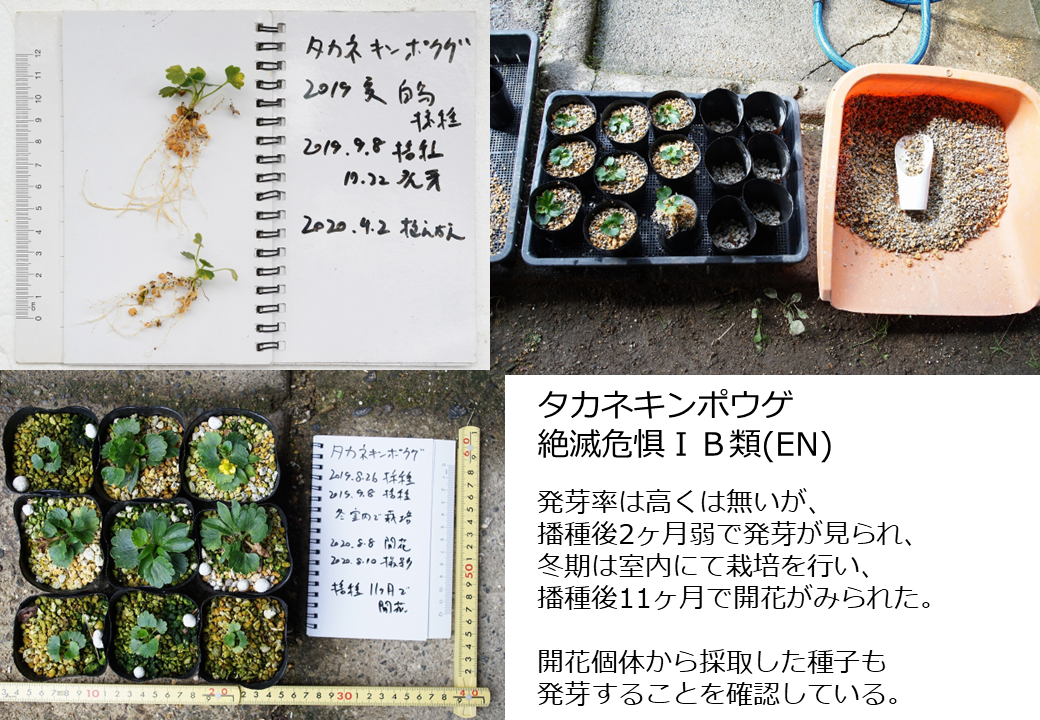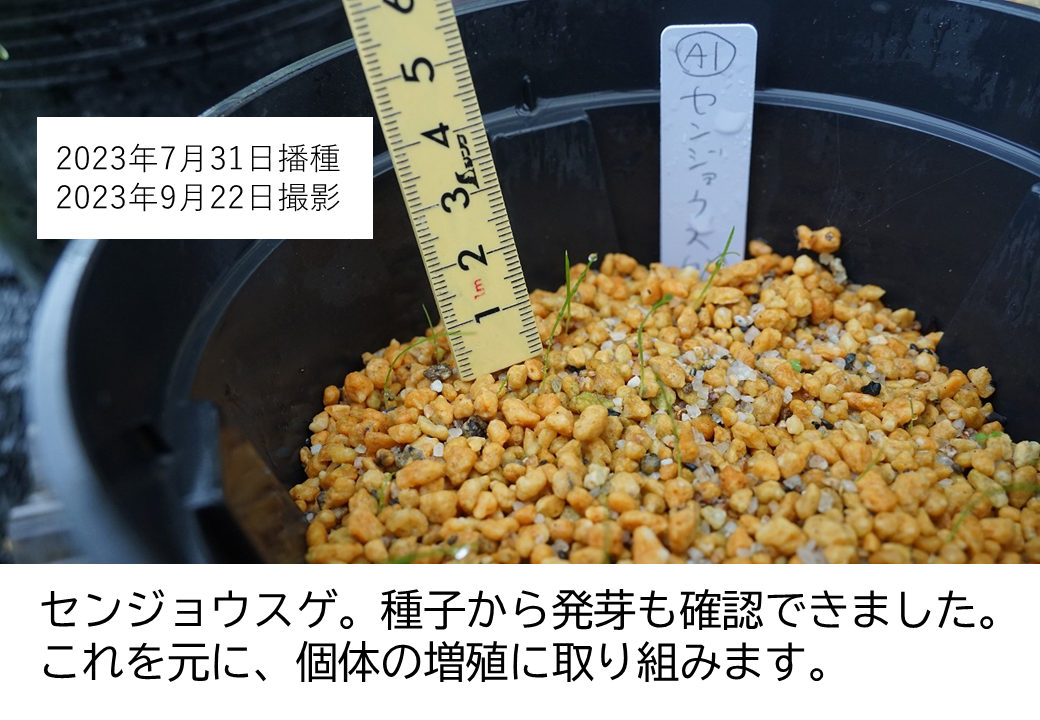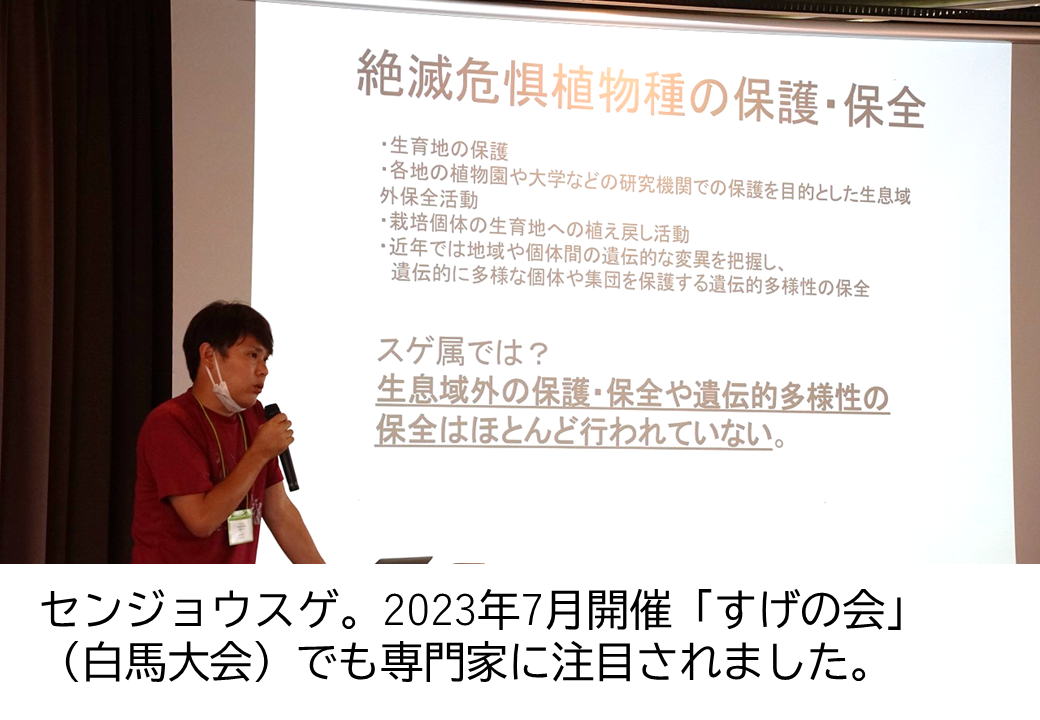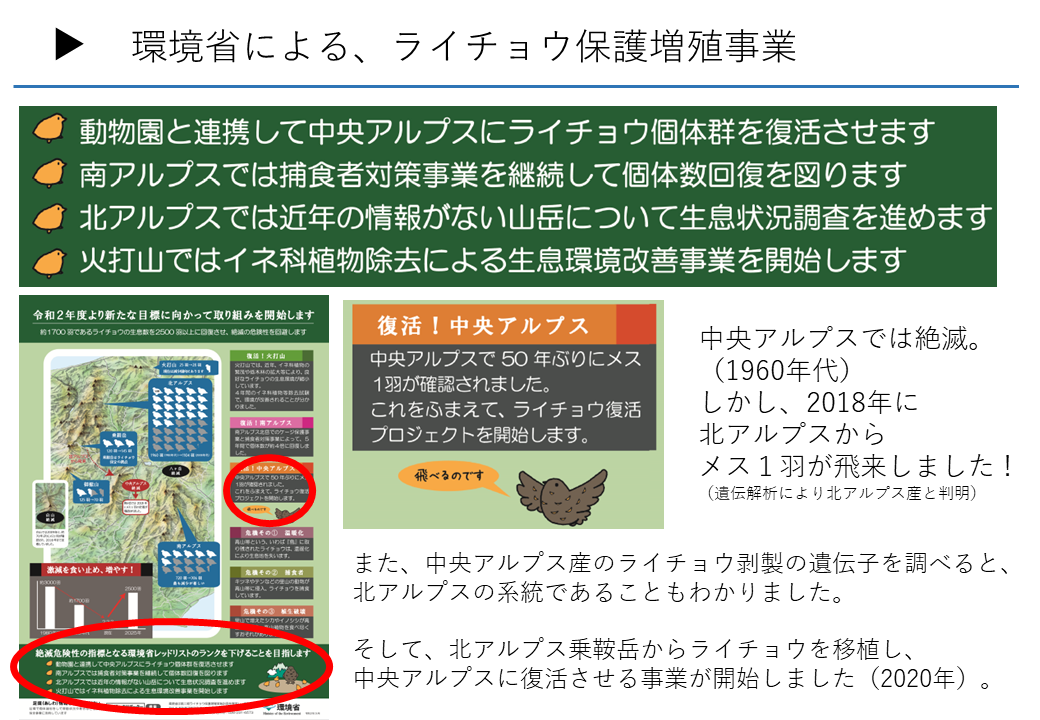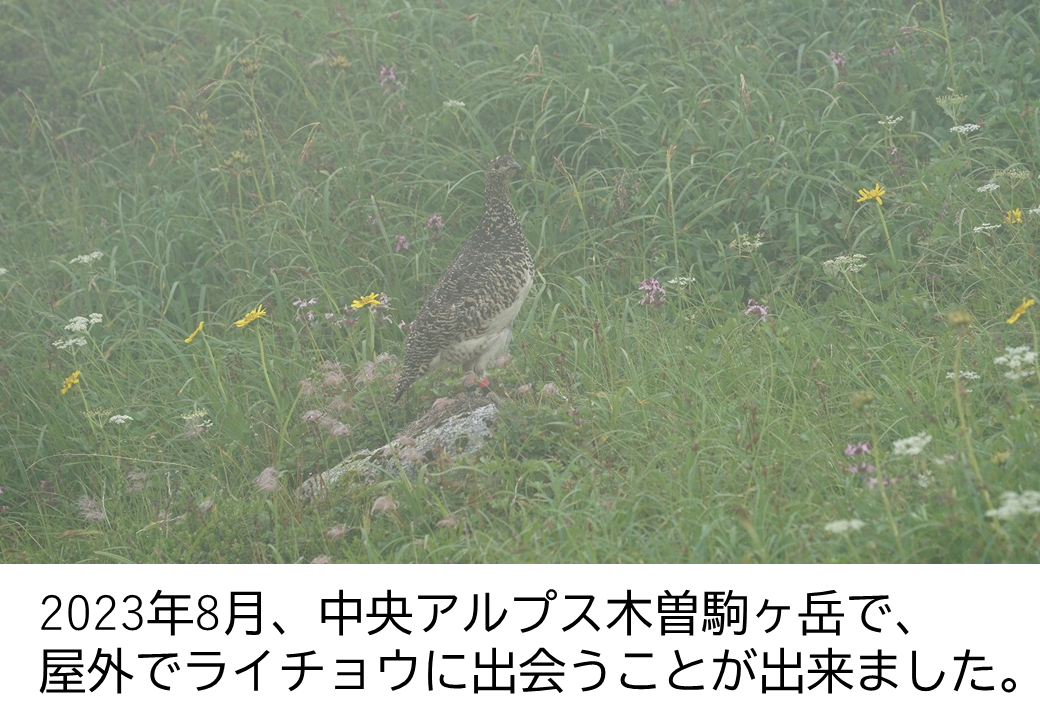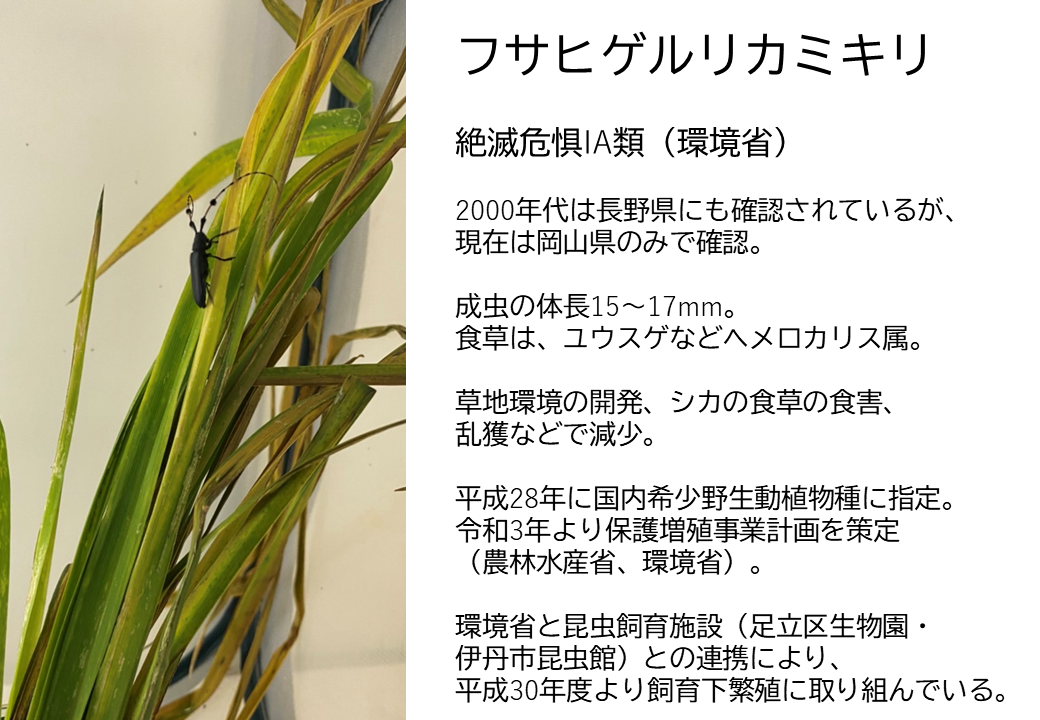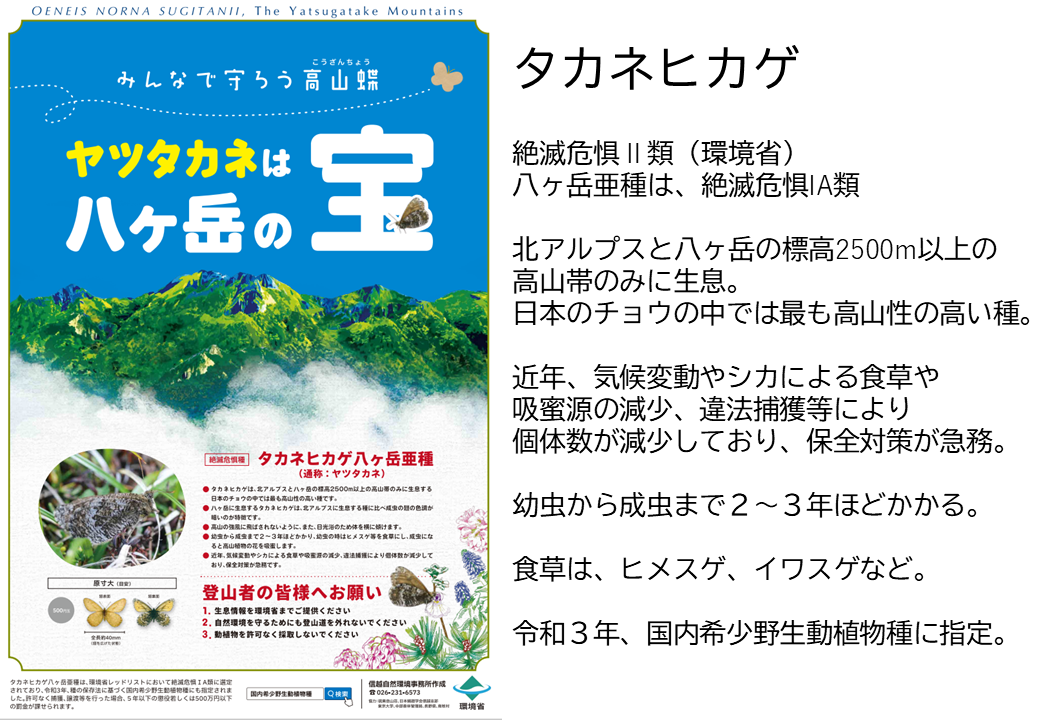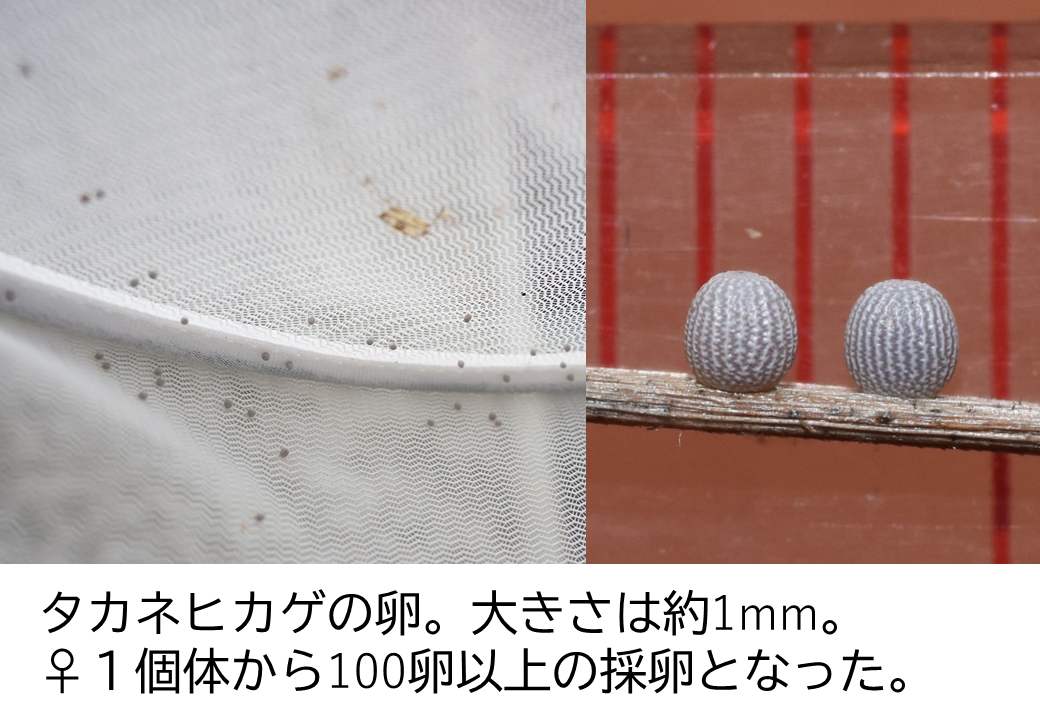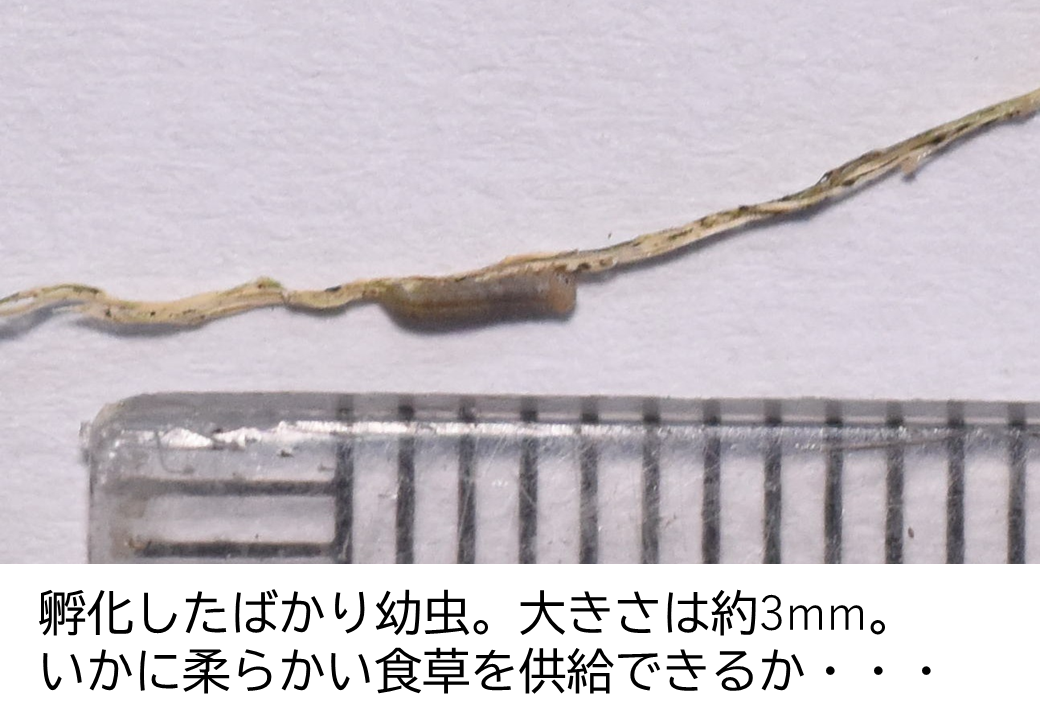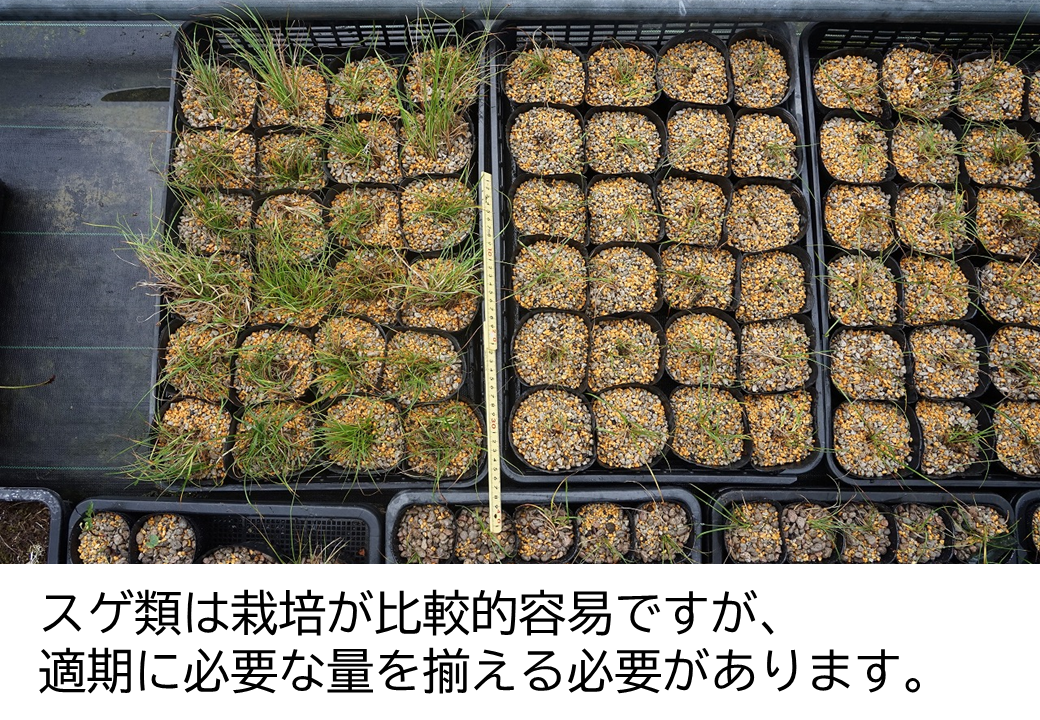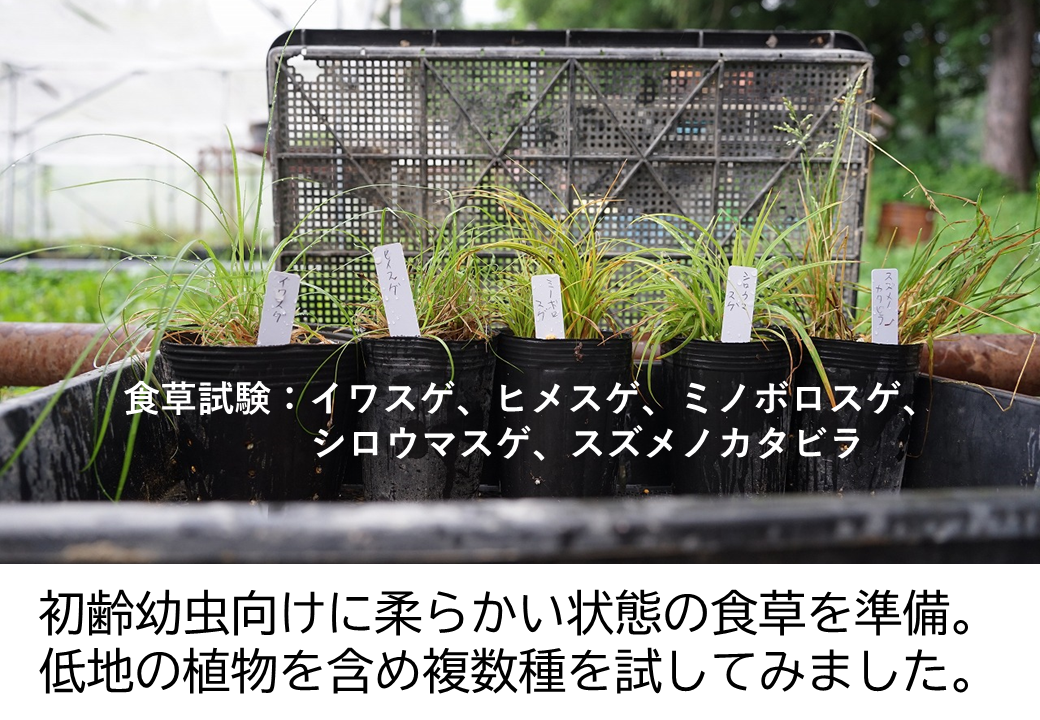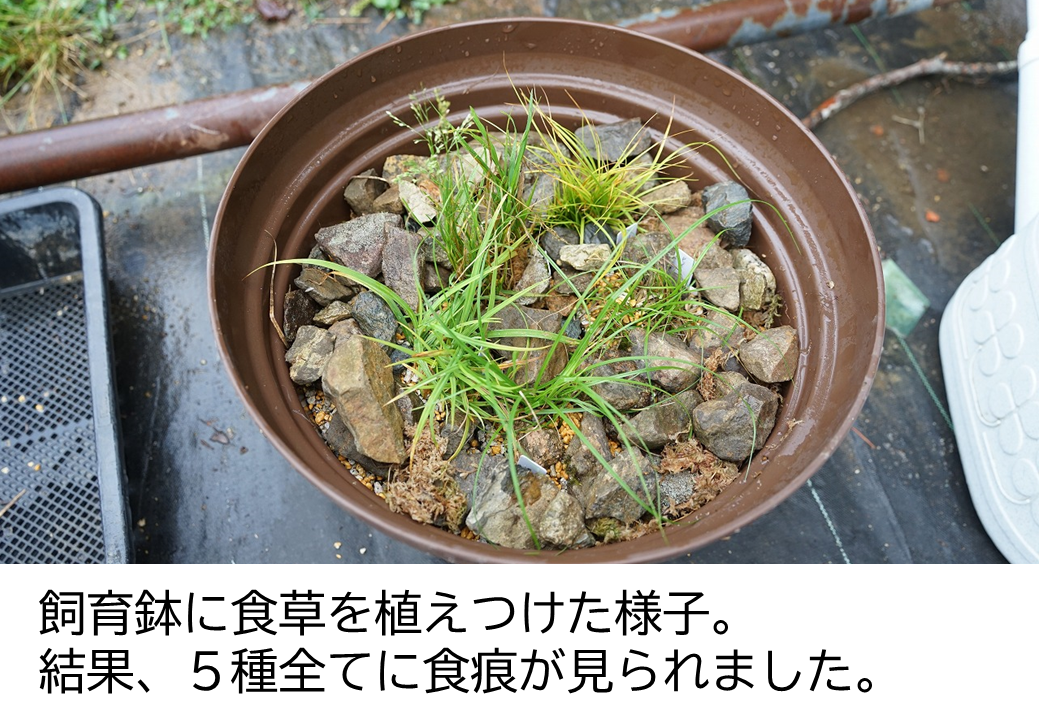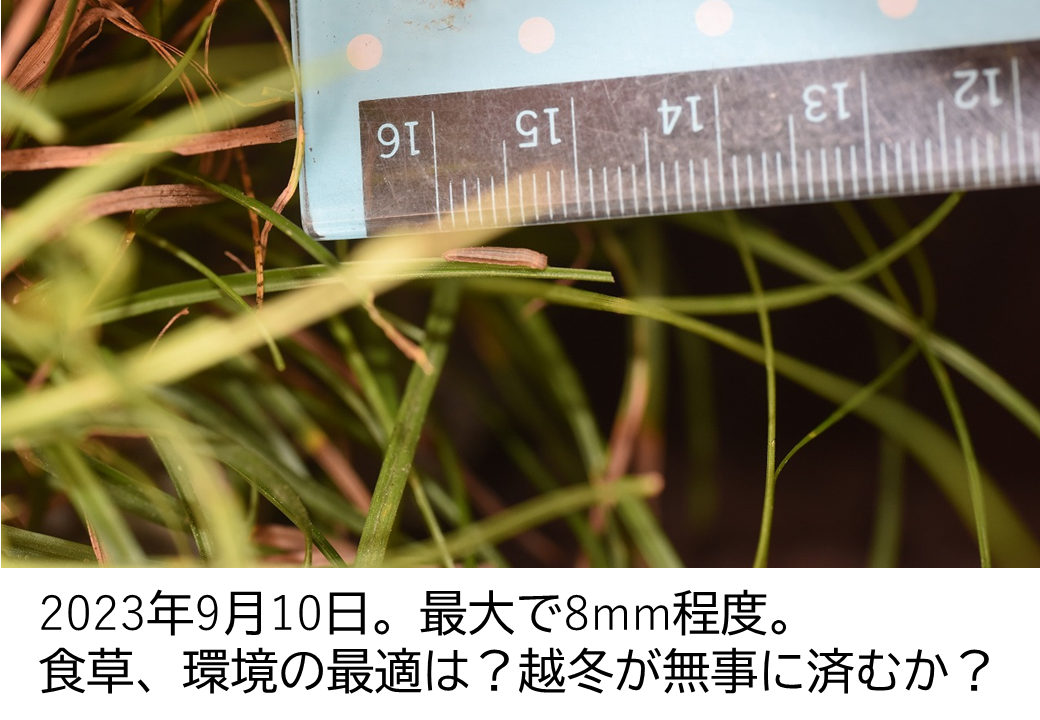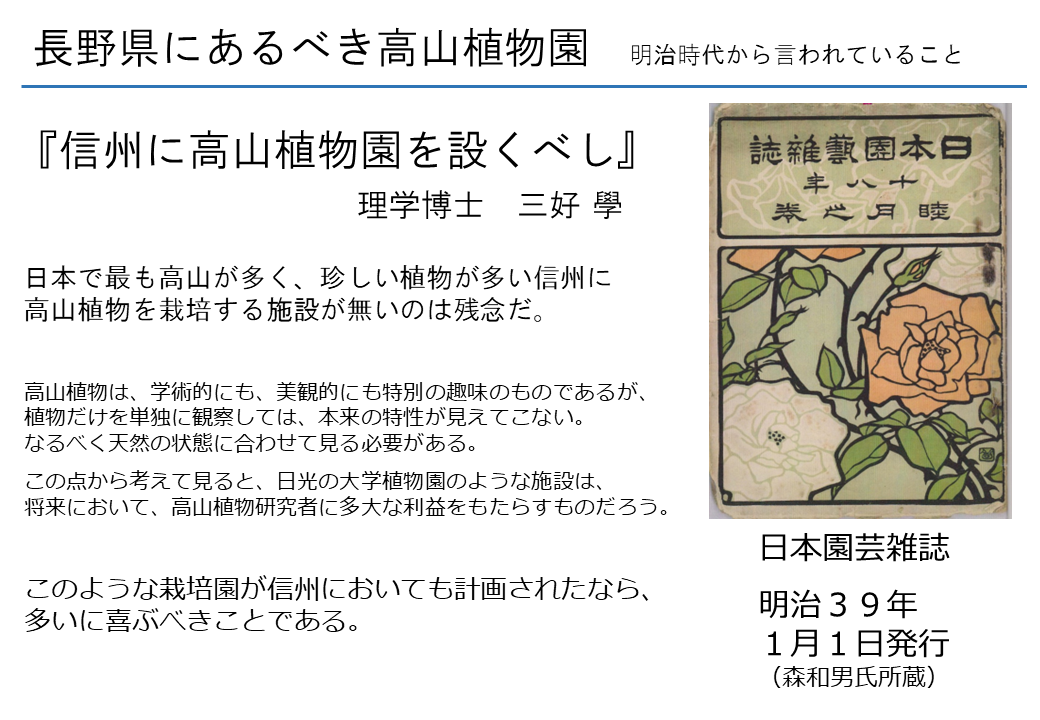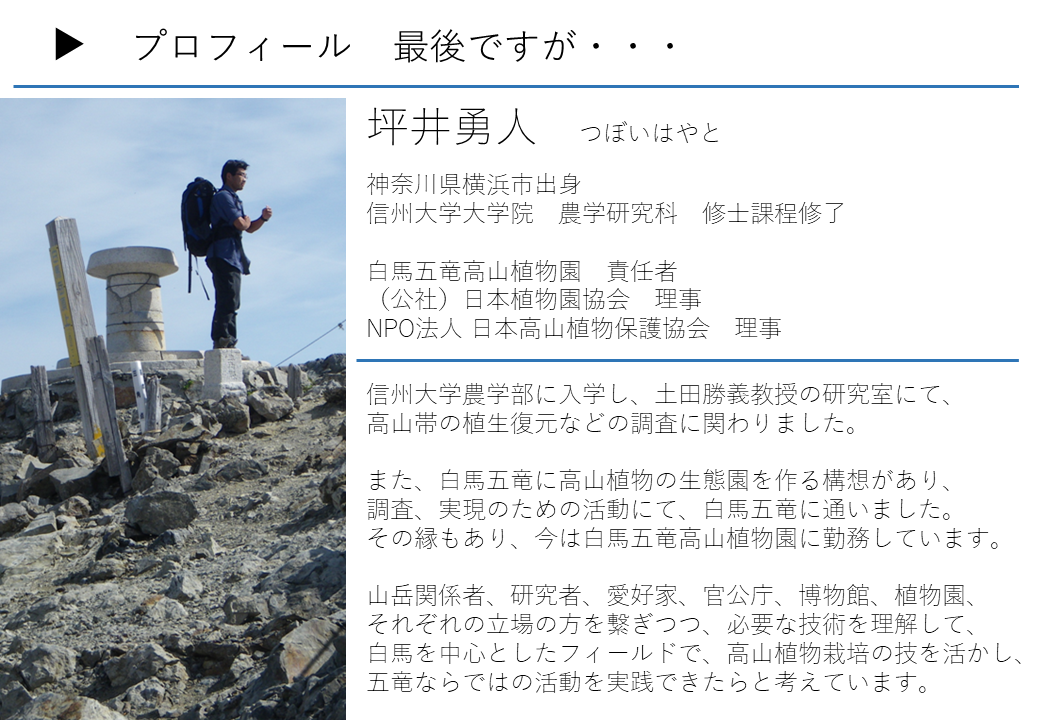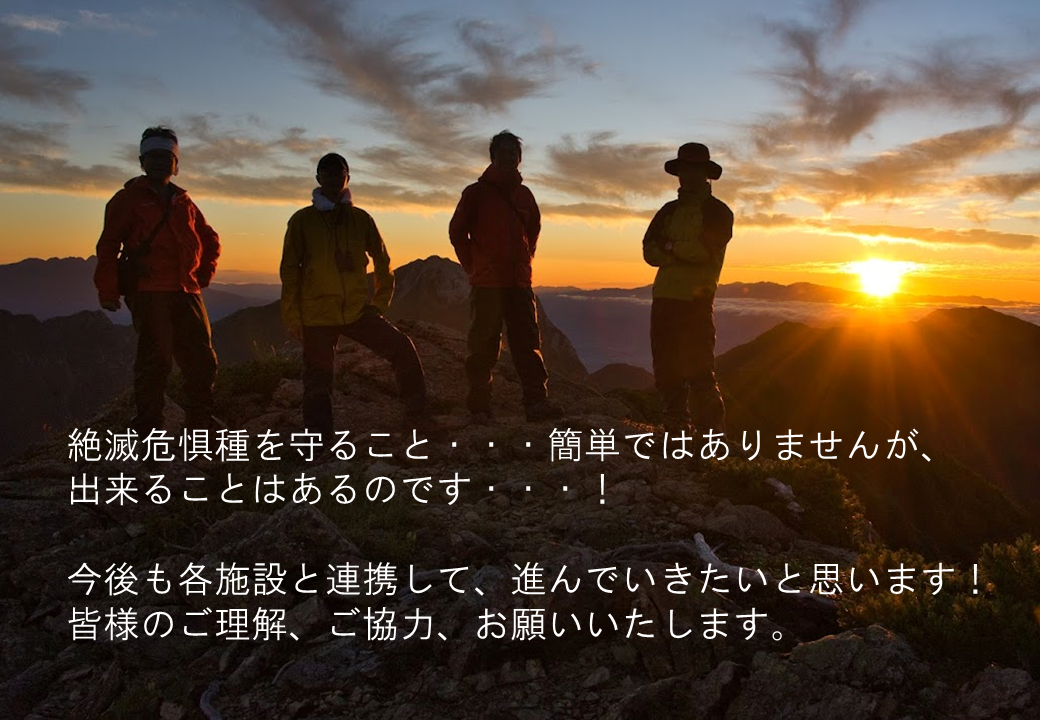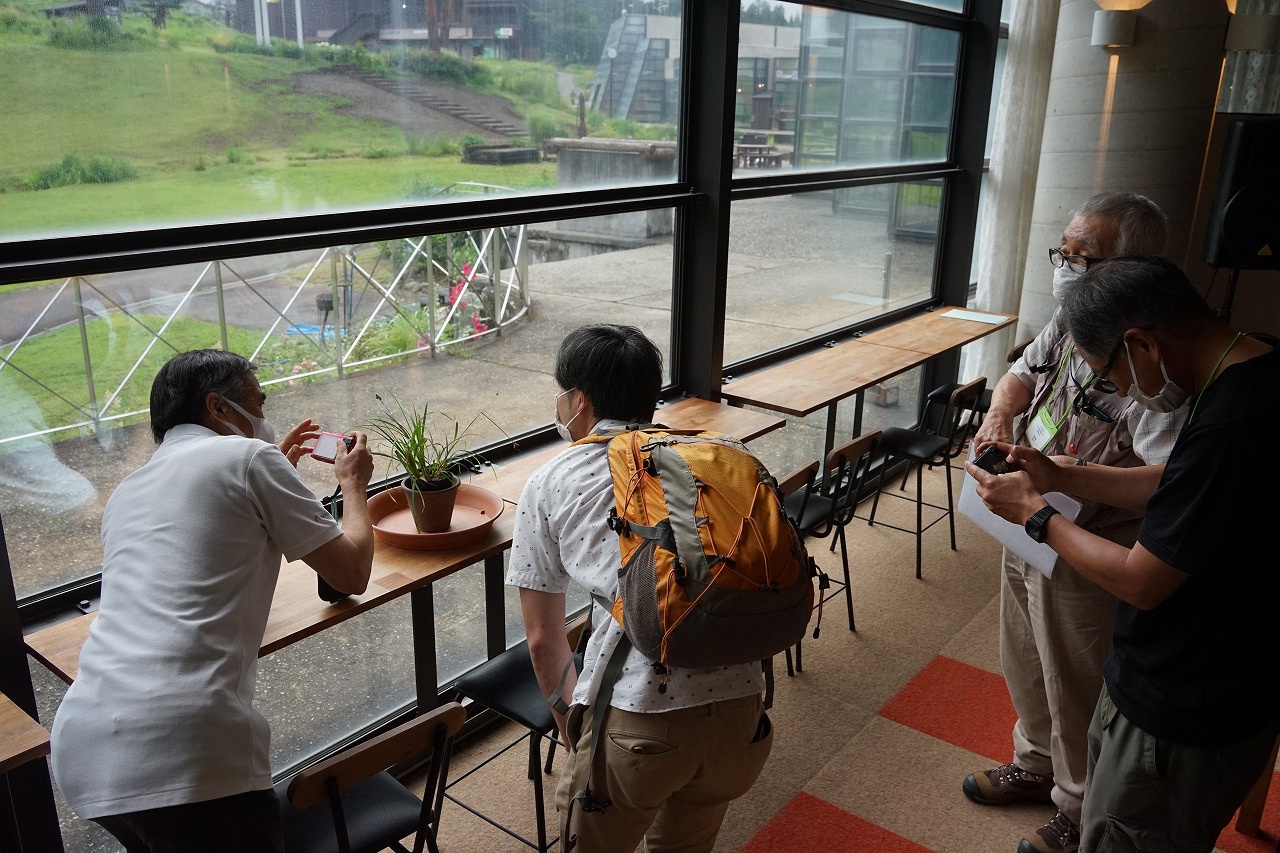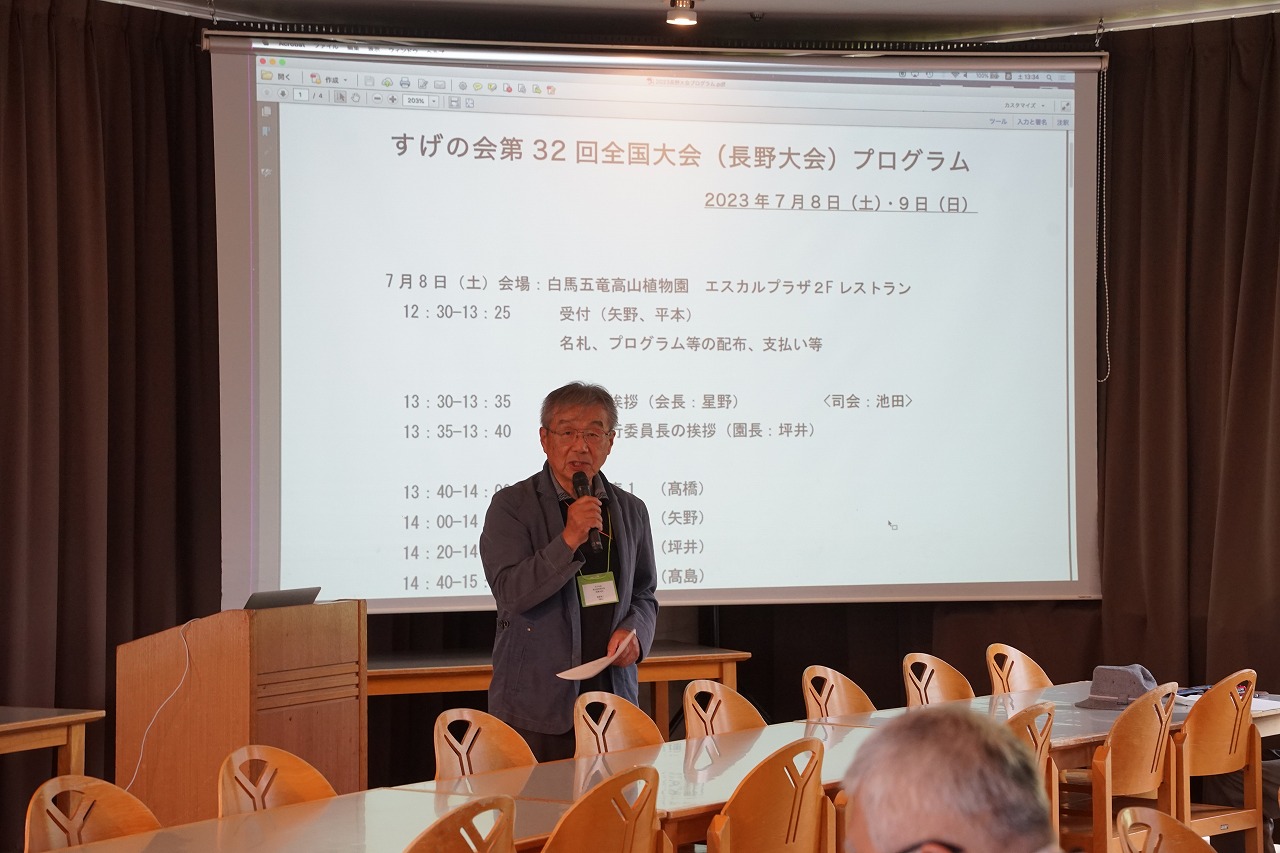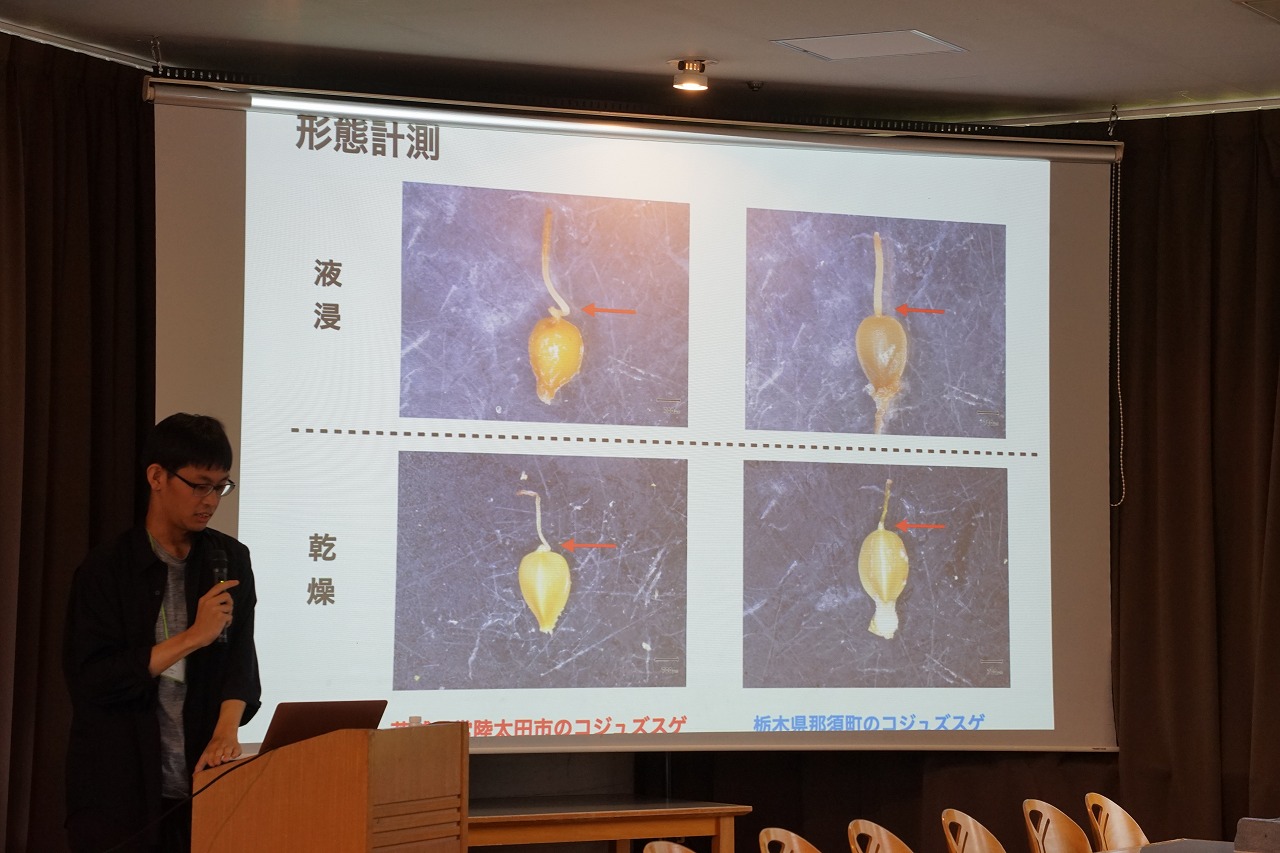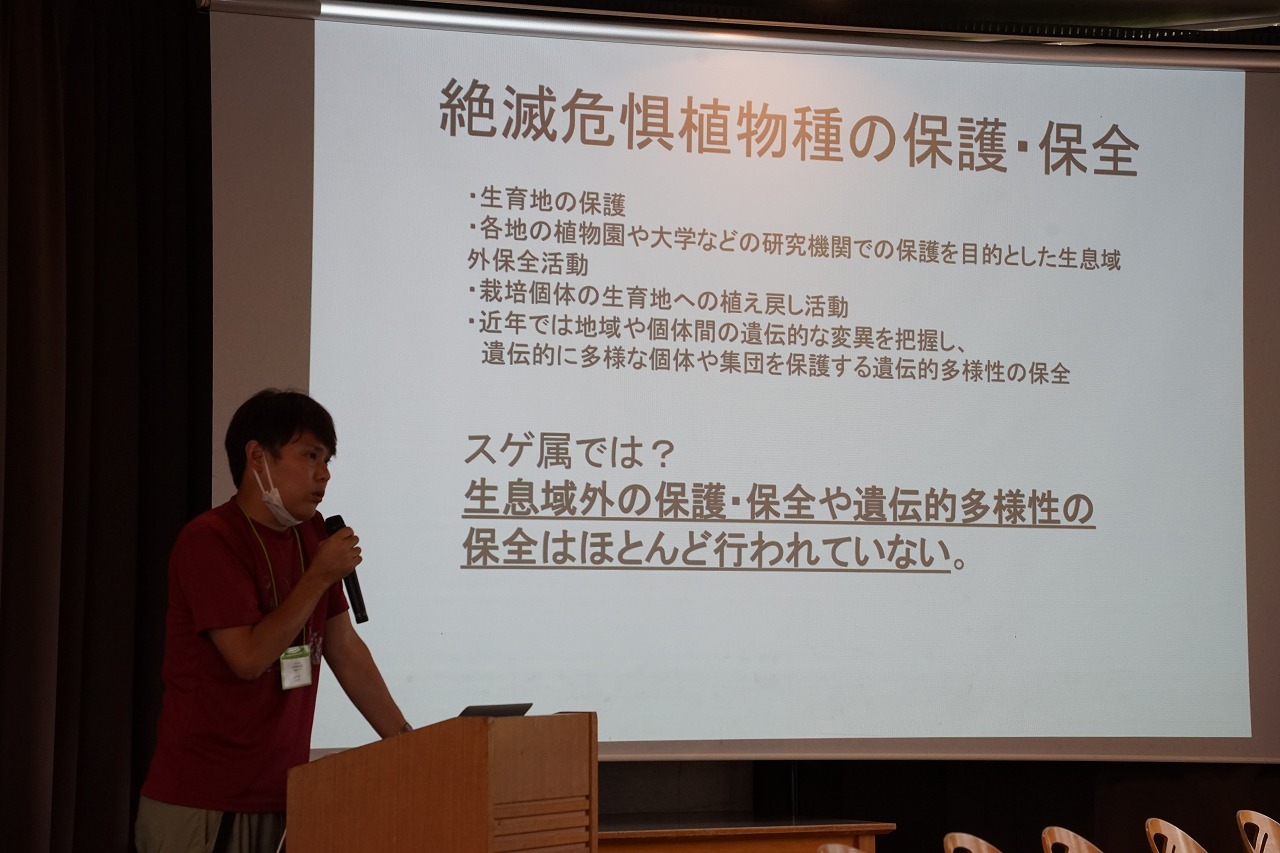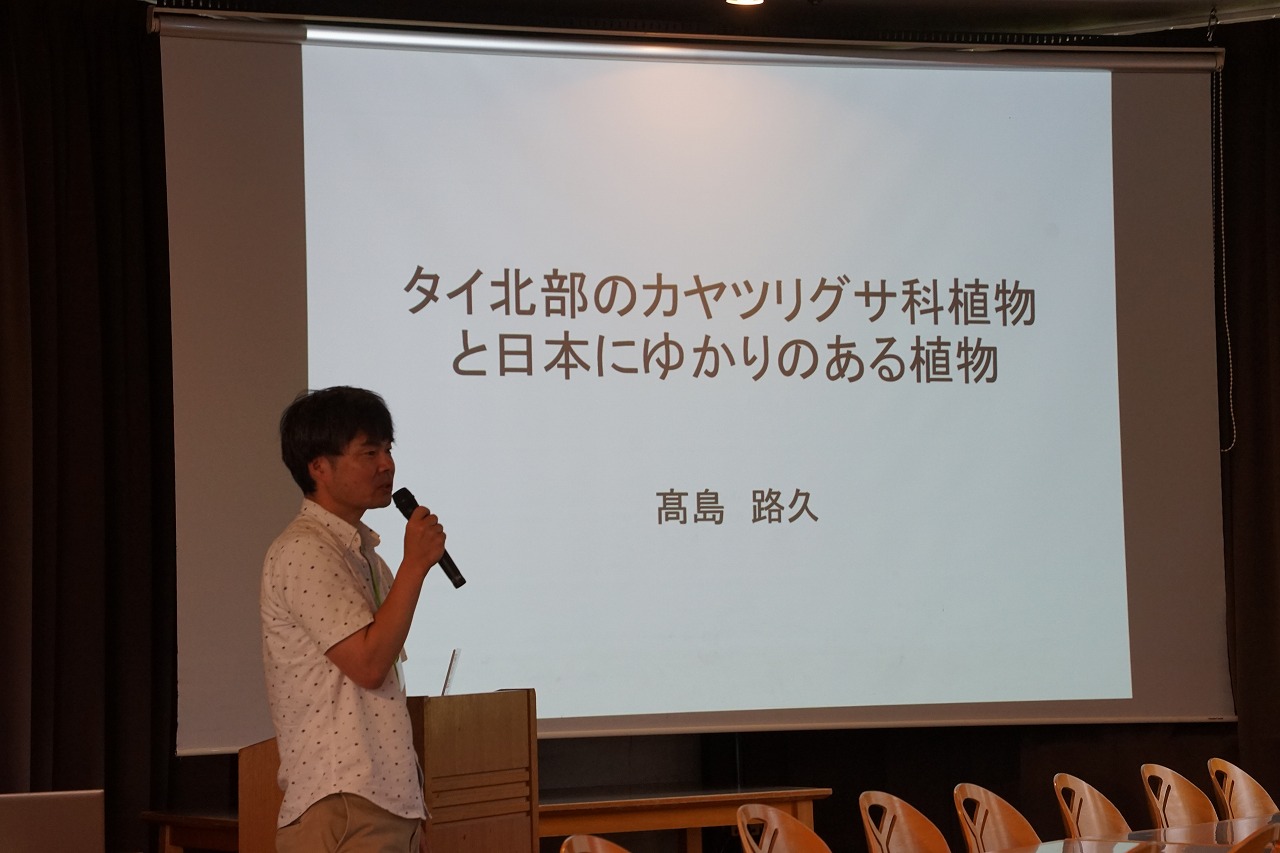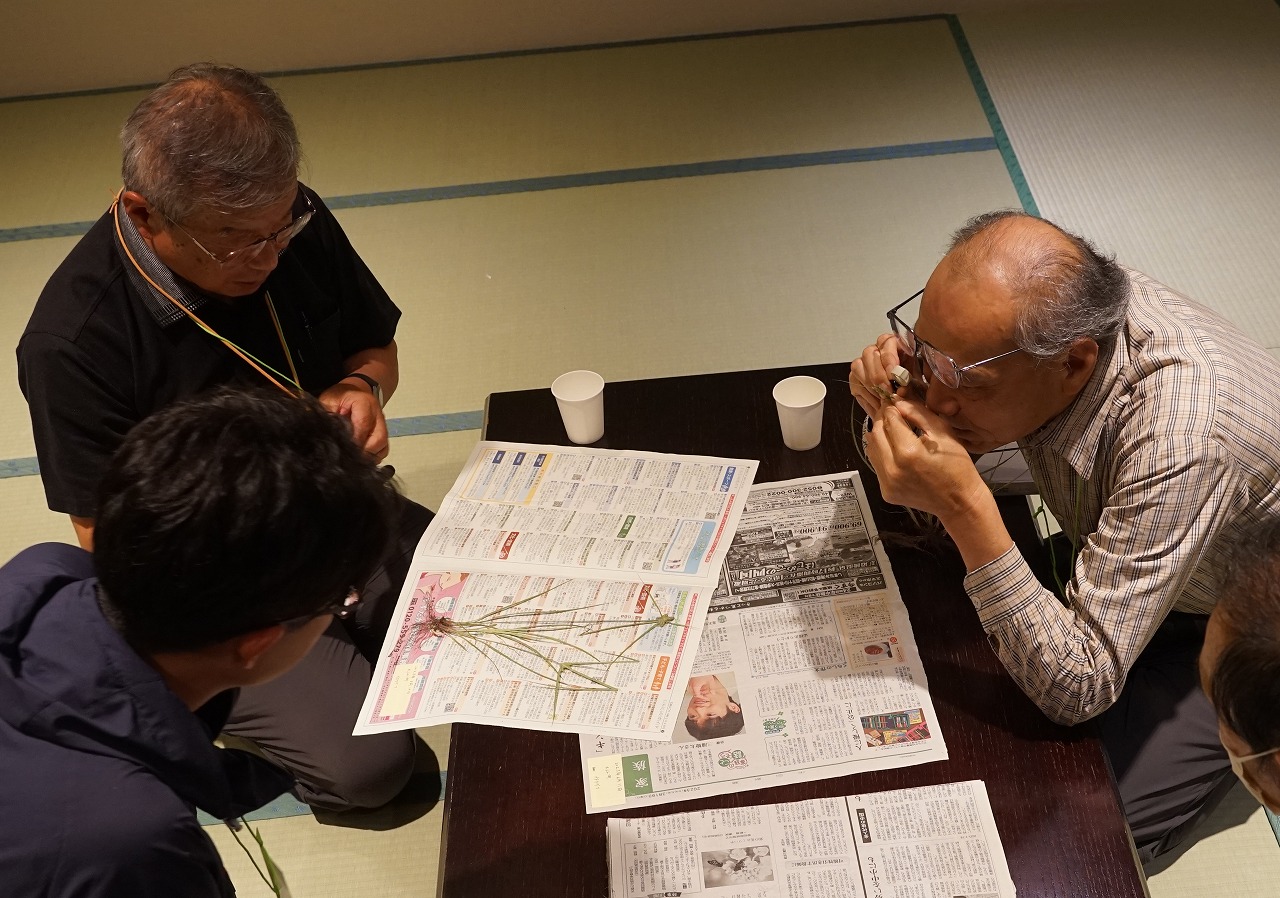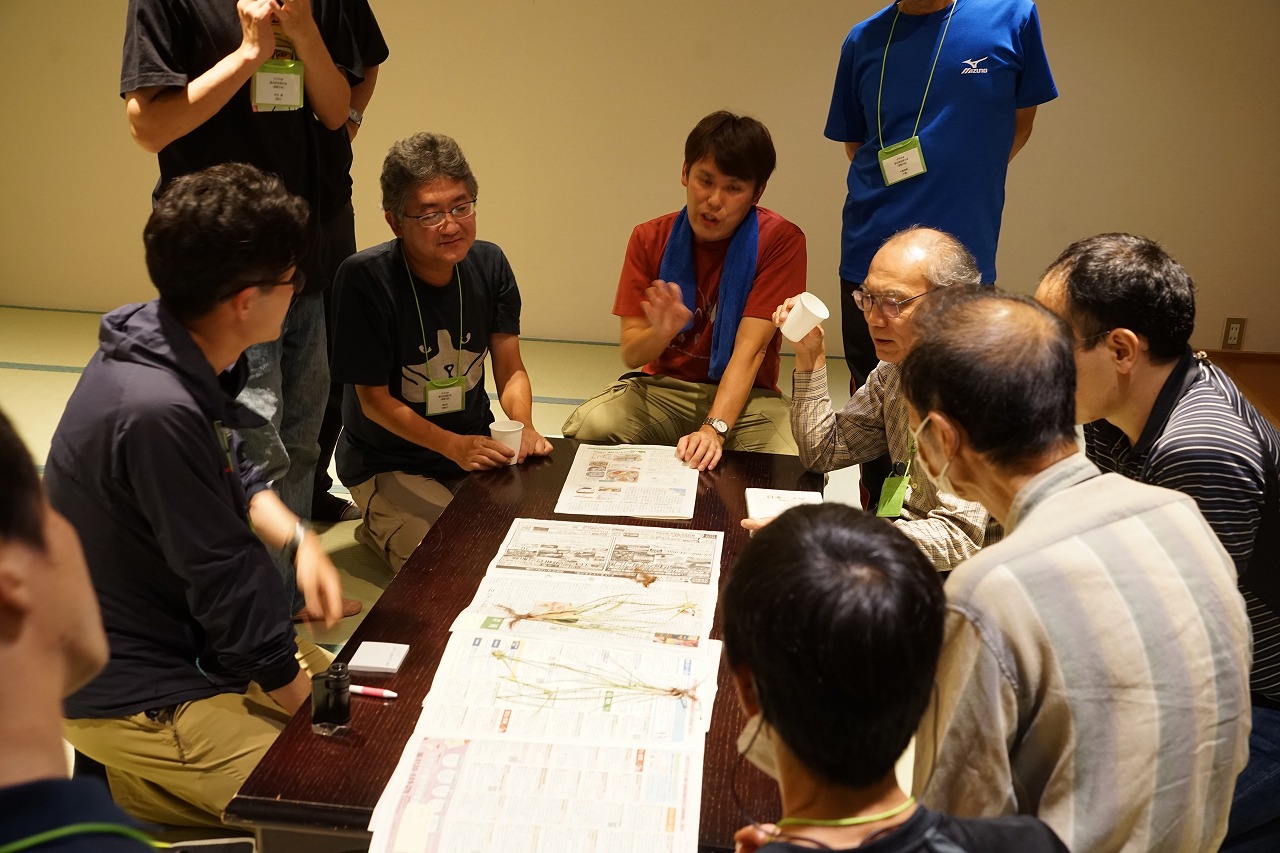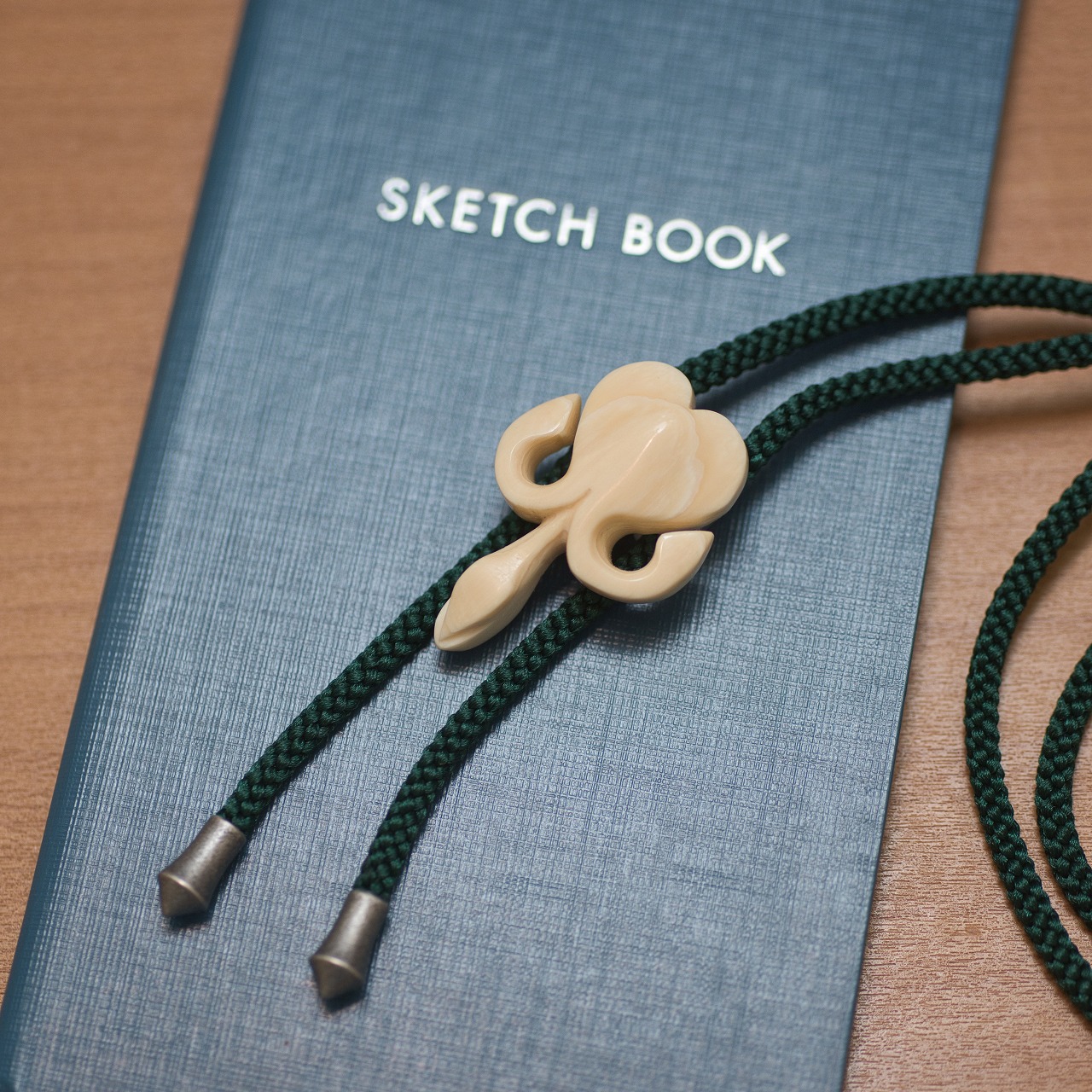こんにちは。白馬五竜高山植物園スタッフ、ひのきです!
まだ8月ですが、白馬五竜高山植物園はもう秋を感じられるようになってきてトンボが飛び回っています。
夏の花と秋の花の共演が見られるのは今!
今日はそんな高山植物たちの紹介をしたいと思います。
第1号は松虫草(マツムシソウ)
紫色の美しい花を咲かせる松虫草。園内でも秋の始まりを感じさせてくれています。この植物の名前の由来は、種子の形が囃子の松虫鉦に似ていることからきていると言われています。秋の風情を感じる一品です。

第2号はビッチュウフウロ
近くによって見て下さい。すごく繊細な花びらがとても綺麗です。また、葉っぱも不思議な形。ガーデンスタッフは花が咲いていなくても葉っぱで見分けることができると言っていました。
ビッチュウフウロですが、備中とは岡山県の旧国名で、岡山県で最初に発見されました。
もともと西日本に多いフウロソウで中国地方から長野県南部までは連続的に分布しているのですが、白馬村には飛地で分布しています。ビッチュウフウロは単に絶滅危惧種というだけでなく、白馬村に隔離的に分布している点で面白い分布の植物だと思います!
大切に育て観察して、いつまでも美しい花をみせてほしいものです。

第3号はヤマユリ
なんと大きな花なんでしょう!初めて見た時びっくりしました。そして香りのいいこと、幸せな気分になります。まだまだ咲いてます、ぜひ見にきてあげて下さい。
ここで五竜の学芸員さんが教えてくれた豆知識。
日本は実はユリの数が多い国なんです!カサブランカなどの有名なユリの品種は実は日本のヤマユリが元になって品種改良されたものなんです。幕末に日本が開国して欧米人が日本にやってきて日本の野生のユリの綺麗さに驚きました。戦前養蚕業が盛んになる前、日本の主な輸出産業はユリの球根だった時代もあったみたいです。

第4号は同じユリだけどイタズラっぽいコオニユリ
鮮やかなオレンジ色が目を惹きます。
なんとコオニユリは実生から4−5年立たないと開花しないのです。生き抜いてきた年月ゆえの美しさですね。
ガーデンも負けていません。目に飛び込んでくるのは、オトギリソウ。
もう一面黄色ってくらい咲いています。
小さい花がたくさんついていてよく見てみるととても可愛いです。可愛い花なのですが、名前の由来には少し怖いエピソードもあります。調べてみると面白いかもしれません。
ご紹介した花々以外にも、まだまだたくさんの植物が咲いています。もう少しすると紅葉も始まりますので、ぜひこの機会に植物園にお越しください。
最新の花情報は「週刊花便り」でチェックしてくださいね💐